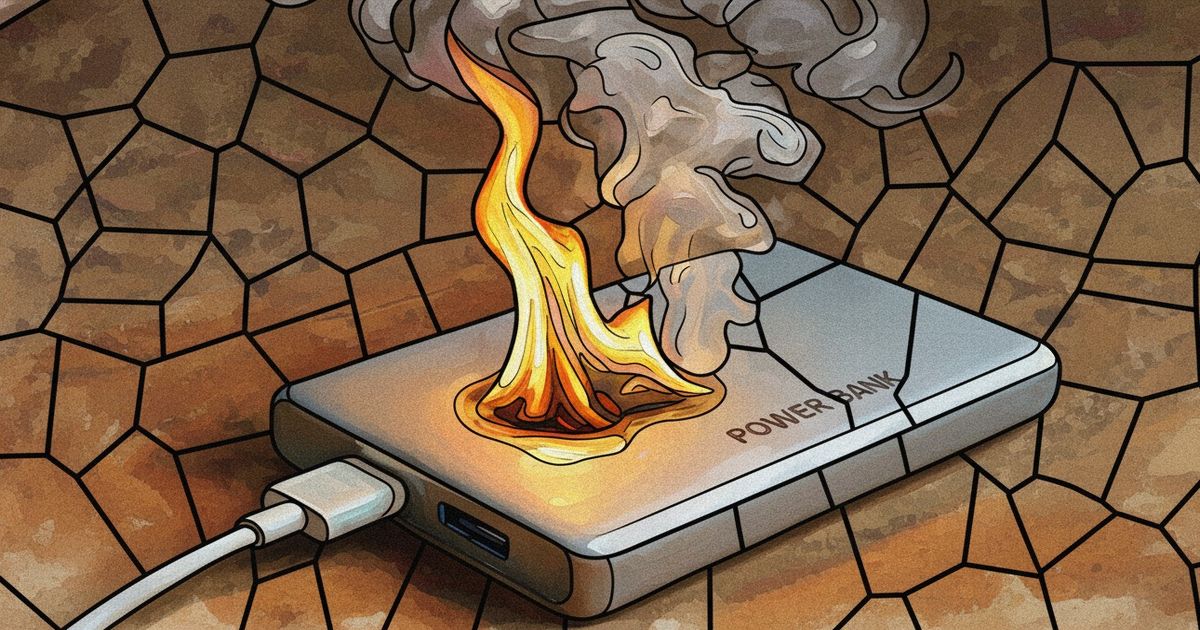※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。
あなたも一度は見たことがあるかもしれません。丸い体にオレンジ色の前歯、そして長いしっぽ――それが今、日本各地で問題となっている「ヌートリア」です。
関連記事
もともとは南米原産の外来種。毛皮目的で輸入されたこの動物が、いま農業地帯で驚異的な勢いで増えています。
田んぼの稲を食い荒らし、野菜畑を荒らす被害が急増するなか、人と自然の“境界線”が改めて問われています。
各地でヌートリア被害が急増 浜松でも確認
近年、静岡県浜松市をはじめ西日本各地で「ヌートリアの目撃情報」が急増しています。浜松市だけで昨年619件の通報があり、農作物の被害報告も18件に上りました。捕獲活動を行う地元の有害鳥獣対策員は、「田んぼやレンコン畑、野菜もすべて食べ尽くす」と語ります。
70センチ近い体長と強靭な前歯を持つヌートリアは、農家にとって大きな脅威となっています。
もしあなたの畑にも地中からの被害があるなら、地面振動で追い出す方法も有効です。
👉 音波振動でモグラを追い出す【モグラ撃退グッズのモグラン】
![]()
害獣対策の第一歩として、環境にやさしく実践できる方法です。
外来種の背景 毛皮目的から野生化へ
ヌートリアは明治時代、毛皮を取るために南米から持ち込まれました。ところが、需要が減ると飼育放棄や逃亡が相次ぎ、野生化。気候が温暖な西日本で繁殖し、今や河川沿いを中心に全国へ拡大しています。
もともと草食で水辺の植物を主食としますが、環境の変化に柔軟に適応し、田畑の作物にも手を出すようになりました。
繁殖力の驚異 年に2〜3回、5〜6匹ずつ出産
捕獲に携わる人の話によれば、「栄養状態が良ければ年に2〜3回産み、1回に5〜6匹」という繁殖力の高さが、急激な個体数増加の原因だといいます。わずか数年で群れが広がり、河川を伝って生活圏内にまで入り込むケースも増えています。
その一方で、ヌートリア自身も天敵が少なく、人の生活圏が“安全地帯”となっているのが現状です。
ヌートリアだけでなく、モグラやネズミの被害も深刻です。
地中振動で近寄らせない方法なら、農地を傷つけずに対策できます。
▶ モグラ撃退グッズのモグラン公式ページを見る
![]()
農家の悲鳴 稲の2割が被害との声も
浜松市のコメ農家の人は、「稲の苗が途中から食べられてしまう」と語ります。被害が出た田んぼでは、稲がまばらになり、青米(未成熟の米)が増加。収穫量全体の2割が失われることもあるといいます。
また、草刈り中にヌートリアに噛まれる事故も報告されており、単なる農業被害にとどまらず、安全面への不安も広がっています。
- 特定外来種に指定され、全国で繁殖が進行
- 田んぼ・野菜畑など農業被害が拡大中
- 泳ぎ・潜水が得意で水辺に生息
- 繁殖力が高く、年間十数匹の子を産む
- 人を噛むなど接触トラブルも発生
専門家の見解 「共生ではなく管理の段階」
外来生物研究者は、「ヌートリアはすでに定着段階にあり、今後は“完全な駆除”よりも“管理と防除”を目的とした対策が必要」と指摘します。
実際、岡山県などでは捕獲後にジビエとしての活用も試みられており、「命を無駄にしない形での管理」が模索されています。
SNSでは賛否両論 「駆除か共生か」
X(旧Twitter)では、「人間のほうが住処を奪っている」と共感する声がある一方、「農家が守れない」と訴える意見も多数見られます。
ある投稿では「かわいいけど、被害を見たら複雑」「共生を語るには現実を知らなきゃ」といった声も。生態への理解と現場の実情、どちらの視点も欠かせないテーマとなっています。
農作物や庭を守るための実践的な防除法を検討するなら、
【モグラ撃退グッズのモグラン】 が効果的です。
![]() 環境にも配慮しつつ、被害を未然に防ぐスマートな選択肢です。
環境にも配慮しつつ、被害を未然に防ぐスマートな選択肢です。
今後の課題と共生の道 “境界線”をどう描くか
外来種問題は、単なる“駆除”だけで解決できません。人の営みと自然環境の接点をどのように設計するかが問われています。
専門家は「人の生活圏と生息地の“緩衝帯”を設ける」「餌を残さない」「農業用水路の構造改善」など、現実的な対策を提案しています。
ヌートリアを“敵”とするだけでなく、生態系の中での位置を理解し、共存可能な距離を模索する時期に来ているのかもしれません。
Q1. ヌートリアを見つけたらどうすればいい?
A. 近づかずに自治体や害獣対策窓口に連絡しましょう。捕獲や駆除は専門職が対応します。
Q2. 餌をあげてもいいの?
A. 禁止されています。餌付けは繁殖を助長し、生態系バランスを崩す原因になります。
Q3. 人を襲うことはある?
A. 基本的にはおとなしい動物ですが、驚いた際などに噛みつくことがあります。距離を保ちましょう。
Q4. 捕まえたヌートリアはどうするの?
A. 特定外来生物に指定されているため、個人が飼育・移動させることは禁止されています。
Q5. 被害を減らすための方法は?
A. 水路の金網設置や草刈りのタイミング調整など、地域ぐるみの対策が効果的です。
まとめ:
ヌートリアの増加は、人間社会の在り方そのものを映す鏡でもあります。
便利さの裏で広がる外来種問題――私たちが自然との距離をどう保つかが、未来の共生の鍵を握っています。