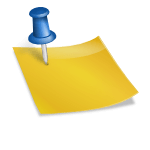2025年11月8日、岡山市の下石井公園には、そんな「犬との暮らし」を見つめ直そうとする飼い主たちが集まった。イベントの名前は「ハレ犬」。ドッグトレーニングの基本を学び、保護犬の現状を知り、人と犬が気持ちよく共存できる社会を考える場だ。大小さまざまな犬たちが集まる公園で、飼い主たちが学んだのは「犬の方から飼い主を見たらおやつをあげる」というシンプルで温かなコミュニケーション法。
そこには、命令や支配ではなく、”会話”を通じた信頼関係を築こうとする姿勢があった。この日、会場には生後1カ月半の保護犬も登場し、岡山市が進める「人馴れ訓練プロジェクト」の取り組みも紹介された。人と犬が共に生きるために、私たちは何を学ぶべきなのか。
岡山市で開かれた「ハレ犬」イベント―集まった飼い主と愛犬たち
2025年11月8日、岡山市の下石井公園で「ハレ犬」と名付けられたドッグトレーニングイベントが開催された。ペットの犬が人と一緒に毎日楽しく生活できるよう、適切な「しつけ」や「コミュニケーション方法」を学ぶことを目的としたこのイベントには、大小さまざまな犬たちと、その飼い主たちが集まった。
会場となった下石井公園は、岡山市中心部に位置する市民憩いの場。普段は子どもたちの遊び場や散歩コースとして親しまれているこの公園が、この日は「人と犬の関係を見つめ直す学びの場」へと変わった。参加者たちは、ドッグトレーナーから直接指導を受けながら、愛犬とのコミュニケーションを深める方法を実践的に学んだ。
イベントの主催は岡山市庭園都市推進課。同課の小林昌樹さんは、「取り組みを通じて人と動物が気持ちよく公園で過ごせるような空間を作っていきたい」と語った。公園は本来、すべての人が快適に過ごせる公共空間だ。しかし近年、犬の吠え声や排泄物の処理、リードを外した状態での散歩など、マナーに関するトラブルも少なくない。「ハレ犬」は、そうした課題に対する一つの答えとして、飼い主の意識向上と実践的なトレーニングの場を提供する試みでもある。
「犬の方から見たらおやつをあげる」―トレーニングの核心
このイベントで飼い主たちが学んだトレーニング方法は、一見すると驚くほどシンプルだ。それは「犬の方から飼い主を見たら、おやつをあげる」というもの。一般的に「しつけ」と聞くと、「お座り」「待て」といった命令を教えるイメージが強い。しかし、今回のトレーニングは命令や強制ではなく、犬が自発的に飼い主に注目する行動を「褒める」ことで、信頼関係を築くことに重点を置いている。
参加した飼い主の一人は、「犬と人が会話をするようにお散歩をするのが幸せなことでもあるので、目が合う回数をお散歩の中で増やしていきたい」と語った。この言葉には、犬を「従わせる対象」ではなく、「対話する相手」として見る姿勢が表れている。犬が飼い主を見るという行動は、「今どうすればいい?」「何か指示がある?」という犬なりの問いかけだ。その瞬間におやつを与えることで、犬は「飼い主を見ることは良いことだ」と学習し、散歩中も自然と飼い主に注目するようになる。
このトレーニング法は、動物行動学の「正の強化」という原理に基づいている。罰や叱責ではなく、望ましい行動をした瞬間に報酬を与えることで、犬はその行動を繰り返すようになる。結果として、リードを引っ張る、他の犬に吠える、拾い食いをするといった問題行動が減り、飼い主と犬の双方にとってストレスの少ない散歩が実現するのだ。
📌 「ハレ犬」イベントの要点まとめ
- 2025年11月8日、岡山市の下石井公園で「ハレ犬」ドッグトレーニングイベントが開催
- 「犬の方から飼い主を見たらおやつをあげる」という正の強化トレーニングを実践
- 岡山市庭園都市推進課が主催し、人と犬が気持ちよく公園で過ごせる空間づくりを目指す
- 会場には生後1カ月半の保護犬も登場し、「人馴れ訓練プロジェクト」の取り組みを紹介
- 命令や強制ではなく、対話と信頼関係を重視したコミュニケーション法を学ぶ場に
保護犬の「人馴れ訓練プロジェクト」―もう一つの取り組み
「ハレ犬」イベントのもう一つの目玉は、岡山市が進める「人馴れ訓練プロジェクト」の紹介だった。会場には、市が保護した生後1カ月半の子犬が登場し、参加者たちの注目を集めた。この小さな命は、まだ人間社会のルールを何も知らない。しかし、岡山市はこうした保護犬たちに「人に馴れる」訓練を施してから譲渡を進めるという、先進的な取り組みを行っている。
日本では毎年、多くの犬が保健所や動物愛護センターに収容される。飼い主の高齢化、経済的困窮、引っ越し、そして「飼いきれなくなった」という理由で手放される犬たち。以前は殺処分される運命にあった犬たちも、近年では譲渡活動が活発化し、新しい家族のもとで第二の人生を歩む機会が増えている。しかし、譲渡後に「吠える」「噛む」「トイレを覚えない」といった問題行動が原因で、再び手放されるケースも少なくない。
岡山市の「人馴れ訓練プロジェクト」は、こうした問題を未然に防ぐための取り組みだ。保護された犬たちに対し、保健所の職員やボランティアが人間との接し方、基本的なマナー、他の犬との社会性を教える。人に触られることに慣れさせ、家庭での生活音に慣れさせ、トイレのしつけを始める。こうした訓練を経た犬たちは、新しい家族のもとでもスムーズに生活に馴染むことができる。
イベント会場では、保健所の職員が保護犬の現状について説明していた。「保護犬を迎えることは、命を救うだけでなく、家族に新しい喜びをもたらすことでもあります」と職員は語る。しかし、その一方で「安易な気持ちで迎えるのではなく、最後まで責任を持って飼う覚悟が必要です」とも強調した。保護犬を迎えることは、ペットショップで犬を購入することとは異なる。過去にトラウマを抱えている犬もいれば、高齢で医療費がかかる犬もいる。それでも、人馴れ訓練を受けた犬たちは、新しい家族との生活に適応しやすく、譲渡後のミスマッチを減らす効果が期待されている。
専門家の視点―「しつけ」ではなく「関係づくり」が重要
ドッグトレーナーや動物行動学の専門家は、近年「しつけ」という言葉ではなく「トレーニング」や「コミュニケーション」という表現を好む傾向にある。なぜなら、「しつけ」という言葉には「人間が犬を従わせる」というニュアンスが含まれ、犬の気持ちや意思を無視した一方的な関係性を連想させるからだ。
動物行動学の研究者は、「犬は本来、群れで暮らす社会的な動物です。人間と犬の関係も、上下関係ではなく、信頼と協力に基づくパートナーシップであるべきです」と指摘する。犬が飼い主を見る行動は、犬なりの「コミュニケーションを取りたい」というサインだ。それに応えることで、犬は「この人は信頼できる」と感じ、より穏やかで協調的な行動を取るようになる。
また、トレーニングの専門家は「正の強化」の重要性を強調する。罰や叱責で犬を従わせることは、一時的には効果があるように見えるが、長期的には犬に恐怖やストレスを与え、攻撃性や不安行動を引き起こす原因となる。一方、正の強化、つまり「良い行動をしたら褒める・報酬を与える」という方法は、犬に安心感を与え、自発的に望ましい行動を取るよう促す。
今回の「ハレ犬」イベントで紹介されたトレーニング法は、まさにこの正の強化の原則に基づいている。飼い主が犬を見るのを待つのではなく、犬が飼い主を見る瞬間を待ち、その瞬間に報酬を与える。この繰り返しが、犬と飼い主の間に強い信頼関係を築く土台となる。
SNS・世間の反応―「目が合う散歩」に共感の声
「ハレ犬」イベントの報道を受けて、SNS上では多くの飼い主から共感の声が上がった。「犬と会話するようにお散歩、すごくわかる」「目が合う瞬間が一番幸せ」といったコメントが相次ぎ、犬との日常の中で感じる小さな喜びに共感する人が多かった。
一方で、「リードを引っ張られて困ってる」「他の犬に吠えてしまって恥ずかしい」といった悩みを抱える飼い主も多く、「こういうイベントがもっと全国で開かれてほしい」という要望も見られた。特に、初めて犬を飼う人や、保護犬を迎えた人にとって、トレーニングの基本を学べる場は貴重だ。
また、岡山市の「人馴れ訓練プロジェクト」についても、「保護犬を迎える前にトレーニングしてくれるのは安心」「こういう取り組みが広がれば、殺処分ゼロにもっと近づける」といった肯定的な意見が多く寄せられた。保護犬を迎えることへのハードルが下がり、より多くの犬が新しい家族のもとで幸せに暮らせる可能性が広がることへの期待が感じられる。
ただし、一部には「おやつを使うのは甘やかしでは」「厳しく叱らないと犬は言うことを聞かない」といった意見もあった。これは、旧来の「支配型トレーニング」の考え方に基づくものだが、現代の動物行動学では、こうした方法は犬の精神的健康に悪影響を及ぼすとされている。専門家は、「犬は罰で学ぶのではなく、報酬で学ぶ生き物です」と繰り返し強調している。
今後の課題―人と犬が共生できる社会に向けて
「ハレ犬」のようなイベントは、人と犬の共生を考える上で重要な一歩だ。しかし、こうした取り組みが一過性のものに終わらず、継続的に広がっていくためには、いくつかの課題がある。
まず、飼い主のマナー教育だ。公園や公共の場で犬を連れて歩く際、リードの長さ、排泄物の処理、他の人や犬への配慮など、守るべきルールは多い。しかし、すべての飼い主がこれらを理解し、実践しているわけではない。行政や地域社会が連携し、飼い主向けの講習会やイベントを定期的に開催することが求められる。
次に、保護犬の譲渡促進だ。岡山市の「人馴れ訓練プロジェクト」は素晴らしい取り組みだが、全国の自治体で同様の制度が整っているわけではない。訓練を受けた保護犬を増やし、譲渡後のフォローアップ体制を整えることで、より多くの犬が新しい家族のもとで幸せに暮らせるようになるだろう。
さらに、犬との暮らしに関する正しい知識の普及も重要だ。SNSやメディアでは、可愛らしい犬の動画が人気を集める一方で、犬の飼育には責任とコストが伴うことが十分に伝えられていない。犬の寿命は10年以上、医療費や食費、トリミング代など、年間数十万円の費用がかかることもある。安易な気持ちで犬を迎えた結果、飼いきれなくなって手放すケースを減らすためには、飼う前の情報提供と教育が不可欠だ。
最後に、ドッグランや犬と一緒に過ごせる公共施設の整備も求められる。犬を飼う人が増える中、犬が安全に運動できる場所、他の犬と交流できる場所、そして飼い主同士が情報交換できる場所が必要だ。岡山市の下石井公園のように、人と犬が共に楽しめる空間が全国に広がることが期待される。
FAQ―よくある質問
Q1. 「犬の方から見たらおやつをあげる」トレーニングは、甘やかしになりませんか?
A. いいえ、これは正の強化という科学的に裏付けられたトレーニング法です。犬が望ましい行動(飼い主を見る)をした瞬間に報酬を与えることで、その行動を繰り返すよう促します。罰や叱責よりも、犬のストレスが少なく、長期的に効果的です。
Q2. 保護犬を迎えたいのですが、どこに相談すればいいですか?
A. お住まいの自治体の動物愛護センターや保健所、または動物愛護団体に相談してください。岡山市のように「人馴れ訓練プロジェクト」を実施している自治体もあります。譲渡前に犬の性格や健康状態を確認し、家庭環境に合った犬を選ぶことが大切です。
Q3. 散歩中、他の犬に吠えてしまいます。どうすればいいですか?
A. 他の犬に吠える原因は、恐怖、興奮、縄張り意識など様々です。まずは他の犬との距離を十分に取り、犬が落ち着いている瞬間におやつを与えて「他の犬がいても大丈夫」と学習させましょう。改善しない場合は、ドッグトレーナーに相談することをお勧めします。
Q4. 公園で犬を連れて行く際のマナーを教えてください。
A. リードは短く持ち、他の人や犬に飛びかからないようにしましょう。排泄物は必ず持ち帰り、おしっこの後は水で流す配慮も大切です。また、犬が苦手な人もいるため、近づく前に相手の了解を得ることがマナーです。
Q5. ドッグトレーニングはいつから始めるべきですか?
A. できるだけ早く、子犬の頃から始めるのが理想です。ただし、成犬になってからでもトレーニングは可能です。「犬は何歳になっても学べる」というのが専門家の共通認識です。焦らず、犬のペースに合わせて進めましょう。
まとめ―「会話するように散歩する」幸せを
岡山市の下石井公園で開かれた「ハレ犬」イベントは、犬と人が共に生きるための、小さいけれど大切な一歩だった。「犬の方から飼い主を見たらおやつをあげる」というシンプルなトレーニングは、命令や支配ではなく、対話と信頼を重視する新しい関係性のあり方を示している。
参加者が語った「犬と人が会話をするようにお散歩をするのが幸せ」という言葉には、犬を家族として、パートナーとして見る温かい視点がある。それは、犬を「従わせる対象」ではなく、「共に生きる仲間」として尊重する姿勢だ。
また、岡山市が進める「人馴れ訓練プロジェクト」は、保護犬たちに新しい人生のチャンスを与える素晴らしい取り組みだ。こうした活動が全国に広がり、より多くの犬が温かい家庭で幸せに暮らせる社会が実現することを願いたい。人と犬の共生は、ルールやマナーだけでなく、互いを思いやる心から始まる。目が合う瞬間に感じる小さな幸せを、これからも大切にしていきたい。