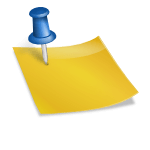東京都心から南約120キロに位置する伊豆大島で、想像を絶する獣害が深刻化している。中国南東部や台湾に生息する小型のシカ科草食獣「キョン」が、島民の3倍を超える約2万1600頭にまで大量繁殖。1970年に都立大島公園の動物園から台風で逃走し野生化したキョンは、特産のアシタバを食い荒らし、「酔っ払った中年男性がえずくような」独特の鳴き声で住民の安眠を妨害している。都は報奨金制度を導入し駆除に乗り出したが、解決のメドは立っていない。産経新聞記者が現地に入り、その凄まじい実態を目撃した。
「グアー」「ギョー」夜明けに響く異様な鳴き声
2025年9月29日、午前5時。伊豆大島の住宅街は、まだ薄暗い。毎朝キョンを見るという女性の散歩に同行した記者は、異様な光景を目の当たりにした。あちらこちらの茂みから、大きくて野太い奇声が反響する。「グアー」「ギョー」。その声は、都の担当者が「酒に酔った中年男性がえずくような声」と表現する通り、人間の嘔吐を連想させる不快な音だった。
キョンの鳴き声は、特にオスが縄張りを主張する際や、メスを呼ぶ際に発する。体長は50〜100センチ程度と小型だが、その鳴き声は驚くほど大きく、野太い。しかも、夜明け前から早朝にかけて活発に鳴くため、島民の安眠を妨害する。ある住民は「毎朝5時頃から『グアーグアー』と鳴き始める。最初は何の音かわからず怖かった」と語る。
関連記事
未明の静寂を破る奇声の反響は、島民にとって大きなストレスとなっている。睡眠不足、精神的疲労。人口約7000人の小さな島で、約2万1600頭ものキョンと共存することの苦痛は、想像を絶する。散歩中の80代女性は「庭に設置したわなで8頭捕獲した」と語り、自宅周辺だけでもこれだけの数が生息していることを明かした。
午後7時過ぎ、記者が同乗した車の50メートルほど先を、子鹿のように小さくかわいらしい動物がとことこと横切った。キョンだ。運転していた一般社団法人「伊豆大島農業生産組合」代表理事の藤田光正さんは、「これまでにも2、3回飛び出してきて車とぶつかったことがある」と語る。交通事故のリスクも、島民の日常に影を落としている。
特産アシタバは全滅、家庭菜園もできない食害の深刻さ
伊豆大島の特産品として知られるアシタバ。健康食品としても人気が高く、島の重要な産業の一つだった。しかし、キョンの大量繁殖により、その状況は一変した。伊豆大島農業生産組合代表理事の藤田光正さんは、残念そうにこう語る。「以前は島のいたるところに生えていたが、キョンに食べ尽くされ、今は全くない」。
アシタバだけではない。畑の作物も被害に遭っている。住宅街で話を聞いた50代男性は、「何でも食べてしまうので家庭菜園もできない」と嘆く。野菜、花、果樹。キョンは草食獣であり、植物であればほぼ何でも食べる。柵を設置しても、小型で身軽なキョンは簡単に飛び越えてしまう。夜間に侵入し、朝には畑が荒らされている。こうした被害が、毎日のように繰り返されている。
食害の影響は、島の経済にも及ぶ。アシタバの生産が壊滅的な打撃を受けたことで、関連産業も衰退。観光客向けのアシタバ製品の売上も減少した。農家は、キョン対策のための柵や網の設置に多額の費用を投じているが、それでも完全には防げない。「もうアシタバ栽培は諦めた」という農家も少なくない。
キョンの食欲は旺盛だ。体重は10〜15キロ程度だが、1日に体重の10%程度の植物を食べる。つまり、1頭あたり1日に1〜1.5キロの植物を消費する。約2万1600頭となると、島全体で1日に約21〜32トンの植物が食べられている計算だ。この膨大な量が、島の植生を根本から変えてしまっている。かつて緑豊かだった伊豆大島の風景は、キョンの食害により大きく変貌しつつある。
1970年の台風が招いた半世紀の悪夢
キョンは、中国南東部や台湾などに生息する小型のシカ科草食獣だ。体長50〜100センチ、体重10〜15キロと、日本のニホンジカに比べて小型で、愛らしい外見を持つ。伊豆大島でキョンが野生化したのは、1970年(昭和45年)のことだった。都立大島公園の動物園で飼育されていた個体が、台風で壊れた柵から逃げ出したのが始まりだ。
当時、逃げ出したキョンの数は数頭だったとされる。しかし、伊豆大島はキョンにとって理想的な環境だった。温暖な気候、豊富な植物、そして何より、天敵となるクマやオオカミがいない。繁殖力が非常に強いキョンは、年に1〜2回出産し、1回に1〜2頭の子を産む。生後6ヶ月で性成熟に達するため、爆発的に数を増やすことができる。
1970年代から1980年代にかけて、キョンの存在は島民にとって珍しい動物として受け止められていた。しかし、1990年代に入ると、その数は急速に増加。2000年代には、すでに深刻な問題として認識されるようになった。都の推計では、2020年時点で約2万1600頭にまで増加。島の人口約7000人の3倍以上だ。小池百合子東京都知事は、「人間さまよりもキョンさまの方が数が多い」と皮肉を込めて表現した。
1970年の台風という自然災害が、半世紀にわたる悪夢を招いた。動物園の管理体制の問題、初期対応の遅れ、外来種の危険性への認識不足。様々な要因が重なり、今日の深刻な事態を生んだ。キョンの野生化は、外来種問題の典型的なケースとして、環境学の教科書にも取り上げられるようになった。
交通事故多発、夜道は恐怖との戦い
午後7時過ぎ、記者が同乗した車の前を、突然キョンが横切った。運転していた藤田さんは、慣れた様子でブレーキを踏む。「これまでにも2、3回飛び出してきて車とぶつかったことがある」。伊豆大島では、キョンとの交通事故が多発している。特に夜間、ヘッドライトに驚いたキョンが突然飛び出してくるケースが多い。
キョンは体重10〜15キロと比較的軽いが、時速40〜50キロで走行中の車に衝突すれば、十分な衝撃となる。車のバンパーやヘッドライトが破損するケースも少なくない。さらに深刻なのは、キョンを避けようとしてハンドルを切り、ガードレールに衝突したり、対向車線にはみ出したりする二次的な事故だ。幸い、人命に関わる重大事故は報告されていないが、島民は常に神経を尖らせている。
夜道の運転は、まさに恐怖との戦いだ。いつ、どこから、キョンが飛び出してくるかわからない。約2万1600頭ものキョンが島内に生息している以上、遭遇の確率は極めて高い。島民の多くは、夜間の運転速度を落とし、常に周囲を警戒している。しかし、それでも事故を完全に防ぐことは不可能だ。
交通事故のリスクは、観光産業にも影響を及ぼしている。伊豆大島は東京から近い観光地として人気があるが、レンタカーで島内を巡る観光客も多い。キョンとの衝突事故が増えれば、観光客の安全にも関わる。島の経済にとって、観光は重要な柱だ。キョン問題は、島のあらゆる側面に悪影響を及ぼしているのだ。
都の駆除対策:報奨金制度と猟銃、わなの改良
深刻化するキョン問題に対し、東京都も対応に乗り出している。2007年(平成19年)から猟銃を使った駆除を開始。専門の猟友会メンバーが、山林や草地でキョンを捕獲・駆除している。しかし、キョンは警戒心が強く、身軽で逃げ足も速い。猟銃による駆除だけでは、繁殖スピードに追いつかなかった。
そこで、都はわなの改良にも取り組んだ。当初使用していたわなは、野良ネコが誤ってかかるケースが多かった。キョンを効率的に捕獲しつつ、他の動物への影響を最小限に抑えるため、わなの設計を見直し、予防策の研究も進めている。現在は、市街地にも住民協力型のわなが設置されている。住民が毎日わなを見回り、キョンが捕獲されていれば通報する仕組みだ。
2025年9月からは、新たに報奨金制度が導入された。住民が市街地に設置されたわなを毎日見回り、キョンの捕獲を通報すれば、1頭につき8000円が支給される。この制度により、住民の駆除への参加意欲を高め、捕獲効率を上げることが狙いだ。実際、散歩中の80代女性が「庭に設置したわなで8頭捕獲した」と語ったように、住民の協力は着実に成果を上げつつある。
都の推計では、2021年(令和3年)に頭数は減少傾向に転じた。猟銃駆除、わなの改良、住民協力の成果が出始めたのだ。しかし、まだ約2万頭が生息している以上、根絶までの道のりは長い。都は根絶を目指す方針を明確にしており、今後も駆除活動を強化していく構えだ。
記者が目撃した伊豆大島の「キョンさま」たちの日常
2025年9月29日、記者は伊豆大島に降り立った。東京から高速ジェット船で約1時間45分。青い海と緑の山々に囲まれた美しい島だが、キョン問題の深刻さは、到着直後から実感できた。港から宿泊施設へ向かう車の中、藤田さんが「あそこにもいますよ」と指差す先には、茂みから顔を覗かせる小型の動物。キョンだ。子鹿のような愛らしい外見だが、その数の多さが異常さを物語っている。
午後7時を過ぎると、キョンの活動は活発になる。車で島内を巡ると、5分ごとに1頭は目撃する。道路脇の草むら、住宅の庭、畑の周辺。どこにでもキョンがいる。藤田さんは「昼間はあまり見かけませんが、夕方から夜にかけては本当に多い」と語る。キョンは夜行性の傾向があり、日中は茂みに隠れ、夕方から活動を始めるのだ。
車を止めて、キョンをじっくり観察してみる。体長は60センチ程度、体重は10キロ前後と推測される。茶色の毛並み、大きな目、白い腹部。確かに愛らしい。しかし、その鳴き声を聞くと、印象は一変する。「グアー!」。突然、近くの茂みから野太い声が響く。まるで人間が嘔吐するような、不快な音だ。記者も思わず身構えた。この声が、毎朝5時から響き渡るのだから、島民のストレスは計り知れない。
翌朝5時、毎朝キョンを見るという女性の散歩に同行した。まだ薄暗い住宅街を歩くと、あちらこちらから「グアー」「ギョー」という鳴き声が反響する。女性は「もう慣れましたが、最初は本当に怖かった。何の動物かもわからなかったし、人間の声のようにも聞こえるから」と語る。鳴き声の主を探すと、10メートルほど先の茂みに、オスのキョンが立っていた。縄張りを主張しているのだろう、大きく口を開けて鳴いている。
散歩を続けると、さらに驚くべき光景を目にした。ある住宅の庭に、5頭ものキョンが集まっているのだ。庭に植えられた花や野菜を食べている。住人の男性に話を聞くと、「毎晩来るんですよ。柵を作っても飛び越えてしまうし、もう諦めました」と肩を落とす。庭に設置したわなで、これまでに3頭捕獲したというが、それでも次々と新しい個体がやってくる。
午前6時、島の中心部に位置する都立大島公園を訪れた。皮肉にも、キョン問題の発端となった動物園がある場所だ。公園内の動物園では、現在もキョンが飼育されている。檻の中で飼育されているキョンと、野生化したキョン。その対比が、この問題の複雑さを象徴している。動物園の職員は「1970年の台風は、まさに想定外でした。それから50年以上経った今も、この問題に苦しんでいる」と複雑な表情を見せた。
午前7時、島の農家を訪ねた。かつてアシタバを栽培していたという農家だ。畑を案内してもらうと、以前はアシタバで覆われていたという場所は、今では雑草がまばらに生えているだけだ。「キョンが食べ尽くしてしまって、もうアシタバは育たない。他の作物も試したけど、全部食べられてしまう」。農家の言葉には、諦めと悔しさが混じっていた。
📊 キョン大量繁殖の時系列フロー
❓ よくある質問(FAQ)
Q1: キョンとはどのような動物ですか?
A: キョンは中国南東部や台湾などに生息する小型のシカ科草食獣です。体長50〜100センチ、体重10〜15キロと、日本のニホンジカに比べて小型で、愛らしい外見を持ちます。しかし、「酔っ払った中年男性がえずくような」独特の野太い鳴き声が特徴です。繁殖力が非常に強く、年に1〜2回出産し、1回に1〜2頭の子を産みます。生後6ヶ月で性成熟に達するため、環境が整えば爆発的に数を増やします。
Q2: なぜ伊豆大島でキョンが大量繁殖したのですか?
A: 1970年に都立大島公園の動物園から台風で逃走したことが始まりです。伊豆大島は、①温暖な気候、②豊富な植物、③天敵(クマやオオカミ)がいない、という理想的な環境でした。繁殖力が強いキョンは、初期対応の遅れもあり、爆発的に数を増やしました。2020年時点で約2万1600頭と推計され、島民約7000人の3倍以上になっています。
Q3: キョンによる具体的な被害は何ですか?
A: 主な被害は、①特産アシタバの全滅、②農作物・家庭菜園の食害(「何でも食べてしまう」)、③交通事故の多発、④鳴き声による騒音(早朝5時頃から「グアー」「ギョー」と鳴く)、です。島の経済にも影響し、アシタバ関連産業の衰退、観光への悪影響も懸念されています。島民の生活全般に深刻な影響を及ぼしています。
Q4: 東京都の駆除対策はどのような内容ですか?
A: 2007年から猟銃駆除を開始し、わなの改良も進めています。2025年9月からは報奨金制度を導入し、住民が市街地のわなを見回り、キョン捕獲を通報すれば1頭8000円が支給されます。2021年に頭数は減少傾向に転じましたが、まだ約2万頭が生息しており、都は根絶を目指す方針です。野良ネコの誤捕獲を防ぐ予防策の研究も進めています。
Q5: キョンのジビエ活用は検討されていますか?
A: 千葉県では捕獲したキョンをジビエとして活用していますが、小池百合子東京都知事は2025年9月の記者会見で、採算面から否定的な見方を示しました。キョンは小型で可食部が少なく、食肉処理にコストがかかるため、経済的に成り立ちにくいと判断されています。東京都は、ジビエ活用ではなく、根絶を目指す方針です。
Q6: この問題から学べる教訓は何ですか?
A: 外来種問題の典型例として、①初期対応の重要性(逃走直後の対応が遅れた)、②動物園などの管理体制の徹底、③外来種の危険性への認識向上、④天敵不在環境での繁殖力の脅威、⑤地域経済・生活への長期的影響、などが挙げられます。1970年の台風という自然災害が、半世紀にわたる悪夢を招いたことは、外来種管理の難しさを物語っています。
外来種問題が問いかける人間の責任
伊豆大島のキョン問題は、外来種問題の典型例であると同時に、人間の責任を問いかける重い課題だ。1970年の台風という自然災害が直接の原因ではあるが、その後の対応の遅れ、動物園の管理体制の甘さ、外来種の危険性への認識不足。これらすべてが、今日の深刻な事態を招いた。キョンという動物に罪はない。彼らは、与えられた環境の中で、ただ生きているだけだ。
記者が目撃した伊豆大島の現状は、想像を絶するものだった。早朝5時から響く「グアー」「ギョー」という野太い鳴き声。食い荒らされた畑、全滅した特産アシタバ、夜道を横切るキョンの影。島民約7000人に対し、キョンは約2万1600頭。まさに「キョンさまの方が数が多い」状態だ。この異常事態が、半世紀にわたって続いている。
東京都は、報奨金制度を導入し、住民協力を得ながら駆除を進めている。2021年に頭数が減少傾向に転じたことは、一定の成果と言える。しかし、まだ約2万頭が生息している。根絶までの道のりは、まだまだ長い。繁殖力が強いキョンは、駆除のペースが繁殖スピードを下回れば、再び増加に転じる可能性もある。継続的な努力が不可欠だ。
各地でクマ被害が相次ぐ中、獣害対応の難しさは改めて浮き彫りになっている。クマもキョンも、人間の活動領域に入り込んできた動物だ。しかし、その背景には、環境の変化、人間の管理の甘さ、自然との共存の難しさがある。伊豆大島のキョン問題は、単なる一地域の問題ではなく、日本全体、ひいては世界が直面する外来種問題・獣害問題の縮図なのだ。
島民の一人が語った言葉が、記者の心に残っている。「キョンは可愛いんですよ。でも、あまりにも数が多すぎる。共存できる数を超えてしまった」。この言葉は、外来種問題の本質を突いている。動物そのものが悪いのではなく、人間が作り出した環境の歪みが問題なのだ。私たちは、この教訓から何を学び、どう行動すべきなのか。
伊豆大島の美しい自然を取り戻すために、東京都と島民は今も戦い続けている。報奨金制度、わなの改良、住民協力。様々な取り組みが進められている。しかし、最も重要なのは、このような事態を二度と起こさないことだ。外来種の管理徹底、初期対応の迅速化、環境への影響評価。キョン問題が私たちに突きつけた課題は、決して軽くない。「酔っ払いがえずく」鳴き声が響く伊豆大島の朝。その異様な光景が、人間の責任と、自然との共存の難しさを、静かに問いかけている。