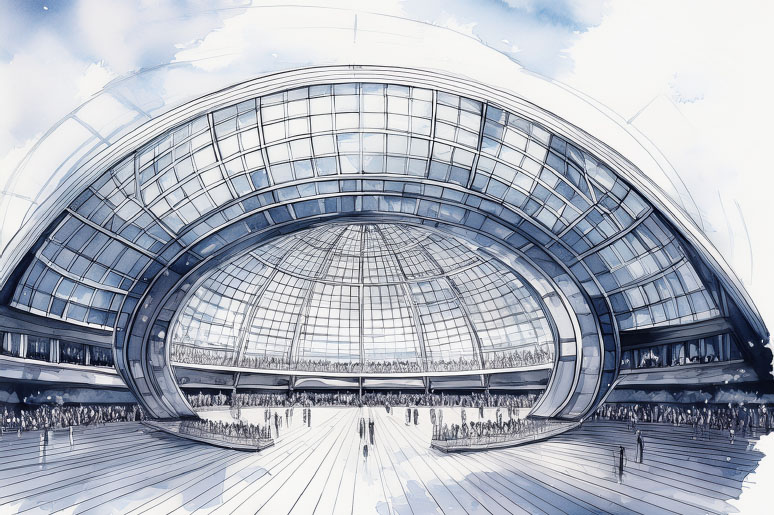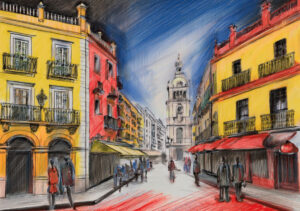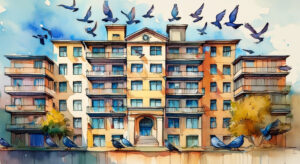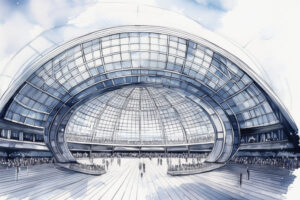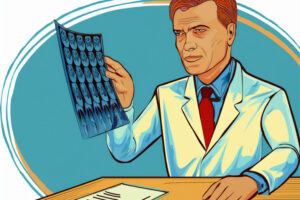北海道浜中町で発見されたラッコの死骸から高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されました。
国内でラッコの感染が確認されたのは初めてであり、海棲哺乳類への拡大が注目されています。
この記事では、感染の経緯や生態系への影響、人へのリスクについて詳しく解説します。
ラッコ死骸からウイルス検出までの経緯

浜中町で子どものラッコが打ち上げられる
北海道が発表した内容によると、2025年4月22日、浜中町藻散布地区の海岸でラッコの死骸が確認されました。
外見的特徴などから、このラッコは子どもであったと見られています。
死骸を回収したのは環境省の野生動物調査チームで、迅速な分析が実施されました。
この調査の結果、ラッコの体内から高病原性鳥インフルエンザウイルス、H5亜型が検出されました。
これにより、国内でラッコが鳥インフルエンザに感染したことが初めて公式に確認された形です。
他の死骸は見つかっていない
ラッコが発見された周辺地域では、その後追加のラッコ死骸は確認されていません。
海鳥の死骸もあわせて監視されており、現時点で同様のウイルス感染がラッコの間で集団発生しているという情報はありません。
環境省と北海道は、今後の追加調査によって、より詳しい生態学的影響や感染経路の特定を目指しています。
海棲哺乳類への感染が広がる背景

海鳥と同じ生息圏が感染の鍵
今回のラッコ感染に関連して注目されているのが、生息地の重なりです。
浜中町沿岸は、ウミウやカモメなど多数の海鳥が飛来する地域であり、ラッコも沿岸の浅瀬を主な活動域としています。
ウイルスが空気中や排泄物によって周囲に拡散される性質を持っているため、海鳥から海棲哺乳類への伝播は自然な経路として考えられます。
特に食物連鎖を通じた感染や、海水中でのウイルスの一時的な生存などが疑われています。
ゼニガタアザラシの感染も確認
2024年末には、浜中町に隣接する根室市でゼニガタアザラシが高病原性鳥インフルエンザに感染していたことが発表されました。
この事例も国内初であり、ラッコへの感染確認と合わせて、北海道東部沿岸で海棲哺乳類にウイルスが広がりつつある実態が明らかになってきました。
ラッコやアザラシなど、海に依存する哺乳類の健康リスクが拡大していることは、生態系全体への影響を示す重要なシグナルといえます。
環境省の対応と今後の監視体制

半径10キロメートルを重点監視区域に指定
ラッコの死骸が発見された海岸を中心に、環境省は半径10キロメートルの範囲を監視重点区域に指定しました。
この範囲では、定期的に海岸線の巡回や空中からの観察が行われ、異常があれば即座に報告される体制が構築されています。
また、地元漁業者や観光関係者に対しても、異変を報告するよう依頼されており、地域ぐるみで感染拡大を防止する体制が強化されています。
遺伝子解析で感染経路を分析中
発見されたウイルスについては、現在専門機関で遺伝子解析が進められており、海鳥や他の哺乳類との関連性を調べています。
遺伝子配列が近い個体が他に確認されれば、感染のルートや拡大範囲を特定する手がかりになります。
今後は、国内全域で発見される野生動物に対する感染検査がより強化されると見られています。
人への感染リスクと注意点

通常の接触で人に感染することは少ない
高病原性鳥インフルエンザは、通常の生活環境において人に感染するリスクは非常に低いとされています。
特に今回のような野生動物を通じた感染は、直接接触や体液などを介した特殊なケースでない限り、人間への感染例はほとんどありません。
一方で、感染リスクが全くないわけではなく、動物の死骸に不用意に触れることは避けるべきです。
死んだ野生動物に触れないよう呼びかけ
北海道と環境省は、死んだり衰弱している野生動物を発見した場合には、素手で触れず、直ちに自治体や関係機関に通報するよう呼びかけています。
特に子どもや観光客が不用意に近づくことを防ぐための啓発活動も強化されています。
正しい知識を持つことが、拡大防止の第一歩とされています。
ラッコが果たす生態系での重要な役割

ラッコは北海道でも特に生息数が限られており、絶滅が懸念されている種の1つです。
海藻を食べるウニの個体数を調整する役割を担い、海の森とも呼ばれる藻場の保全に大きな影響を与えています。
そのため、ラッコの健康は、間接的に海洋環境の健全性を示す指標ともいえます。
鳥インフルエンザのような外部からのウイルス感染が、ラッコを介して生態系のバランスを崩すことが懸念されています。
今後は感染症対策だけでなく、生息地の保護や漁業との共存といった中長期的な視点からの保全が求められています。
今後の展望と課題
高病原性鳥インフルエンザが、陸上から海上へと感染対象を広げていることは、日本における野生動物管理の転換点を意味します。
空を飛ぶ鳥類だけでなく、海に暮らす哺乳類までが対象となることで、監視体制や対応手順もより多様化させる必要があります。
また、観光資源や地域ブランドとしてラッコやアザラシを推してきた自治体では、情報発信の透明性や風評被害の回避も重要な視点となるでしょう。
地域住民、観光業、研究者が協力して、共に感染症リスクに備える姿勢が求められています。
まとめ
- 浜中町で発見されたラッコが、鳥インフルに感染していました。
- ラッコでの感染確認は、国内で初めてです。
- 感染経路は不明ですが、海鳥との接点が指摘されています。
- 根室市では、アザラシにも感染が確認されています。
- 死骸には、触れず速やかな通報が求められています。
- 生態系への影響と、今後の監視体制が課題です。