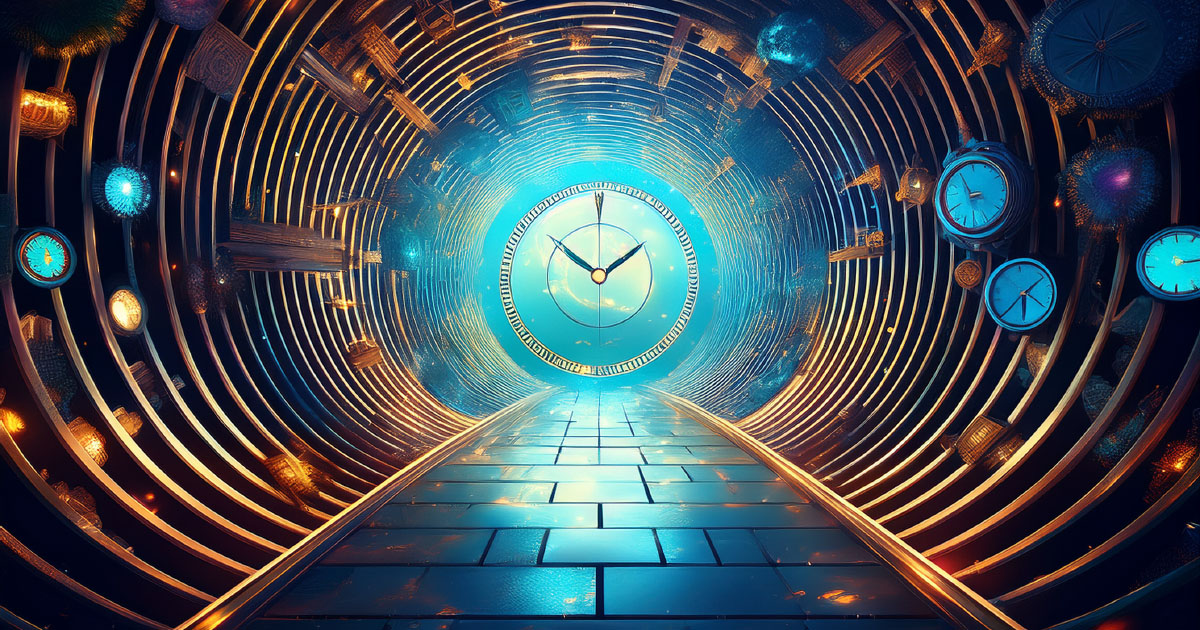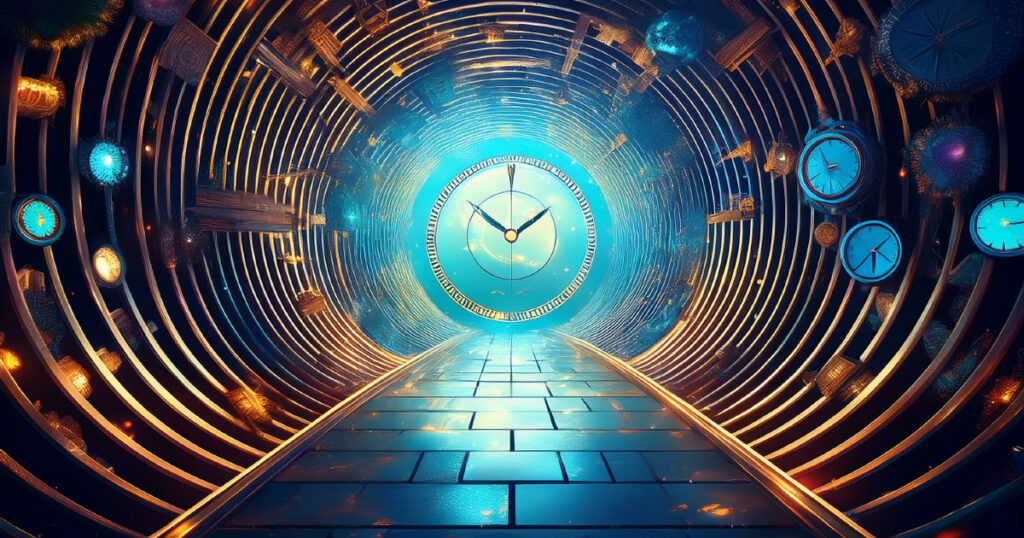日本の漁業が危機的状況に直面している。40年間で漁獲量は1282万トンから363万トンへ激減し、2050年には漁獲ゼロの可能性も。
世界では養殖で生産量が増える中、日本は「一人負け」。漁業者の高齢化や資源管理の甘さが要因とみられる。このままでは食卓から魚が消えるのか? 専門家の意見や解決策を探る。
漁業危機の現状:40年で漁獲量3分の1

日本の漁業は深刻な衰退に直面している。
| 漁獲量 | 1984年1282万トン→2024年363万トン |
| 期間 | 40年間で約3分の1に減少 |
日本の漁獲量は1984年の1282万トンをピークに減少し、2024年には363万トンに。ABEMA TIMESによると、このペースが続けば2050年に漁獲ゼロの可能性もある。
世界の漁業生産量は養殖の拡大で増加する一方、日本は天然資源の過剰漁獲と養殖の停滞で低迷。漁業者の高齢化も進み、従事者数は減少傾向。政府は支援策を検討中だが、抜本的な改革が急務とみられる。
危機の背景:資源管理と構造的問題
なぜ日本だけが漁業で後退しているのか。
| 要因 | 漁獲量規制の甘さと養殖停滞 |
| EEZ | 世界6位の広さ、活用不足 |
日本の漁業は1980年代に世界一だったが、資源管理の失敗が衰退を招いた。
東京海洋大学の勝川俊雄准教授は、天然資源の過剰漁獲と養殖の減少を指摘。
Fisk Japanの片野歩氏は、北欧などの漁業先進国が持続可能性を優先し漁獲枠を厳格化するのに対し、日本は枠が緩く機能していないと説明。
環境副大臣の小林史明氏は、漁獲規制や養殖への法人参入ルールの未整備が課題と述べる。EEZは広大だが、韓国やノルウェーに生産量で抜かれた。
世界との比較:日本の漁業の特異性
日本の漁業は世界とどう違うのか。
| 事例 | ノルウェー:漁獲枠厳格で資源回復 |
| 共通点 | クロマグロ漁獲規制で成果 |
ノルウェーでは漁獲枠を資源量に基づき厳しく設定し、2カ月で上限に達する運用で資源を維持。対して日本は、漁獲枠が実績の倍程度でブレーキ機能がなく、過剰漁獲が続く。
WCPFCのクロマグロ規制は2017年から2023年に資源回復の成果を上げたが、日本全体では同様の成功例が少ない。
片野氏によると、世界では漁獲枠未設定の魚種はほぼなく、日本のTAC(漁獲可能量)運用は特異で、小型魚の乱獲を招いている。
SNSの反応:危機感と解決策への期待
ネット上では漁業危機に驚きと議論が広がる。
| 肯定 | 規制強化で資源回復を望む声 |
| 否定 | 漁業者の生活懸念する意見 |
Xでの反応は賛否両論。ABEMA TIMESの記事に1105件のコメントが寄せられ、危機感を共有する声が多い。「魚が食卓から消える」「規制が必要」との意見が目立つ一方、
漁業者の収入減を心配し「補助金で支えてほしい」との声も。海外の厳格な管理を参考にすべきとの提案や、日本の食文化への影響を危惧するコメントも見られた。持続可能な漁業への転換を求める意見が主流とみられる。
専門家の見解:可能な漁業への転換
専門家は抜本的な改革を求める。
、漁獲枠が緩すぎる日本の現状を批判し、ノルウェーのような厳格な管理が必要と主張。TACの運用が世界と乖離し、小型魚の乱獲を招いたと分析している。
漁獲規制と養殖振興のルール整備を提案。クロマグロの回復例を挙げ、漁業者の収入減対策として補助金を活用しつつ、資源管理を強化すべきと強調しています。
今後の見通し:漁業再生への課題
日本の漁業は再生可能か。
日本の漁業は、資源管理の強化と養殖振興が急務。政府は漁業者支援策を検討中だが、漁獲枠の厳格化や法人参入のルール整備が遅れている。
専門家は、補助金で漁業者の生活を支えつつ、漁獲量を減らす政策が必要と指摘。クロマグロの回復例から、適切な管理で資源は回復可能とみられる。
2050年までに漁獲ゼロを回避するには、早急な改革が不可欠。持続可能な漁業への転換が日本の食文化を守る鍵となる。