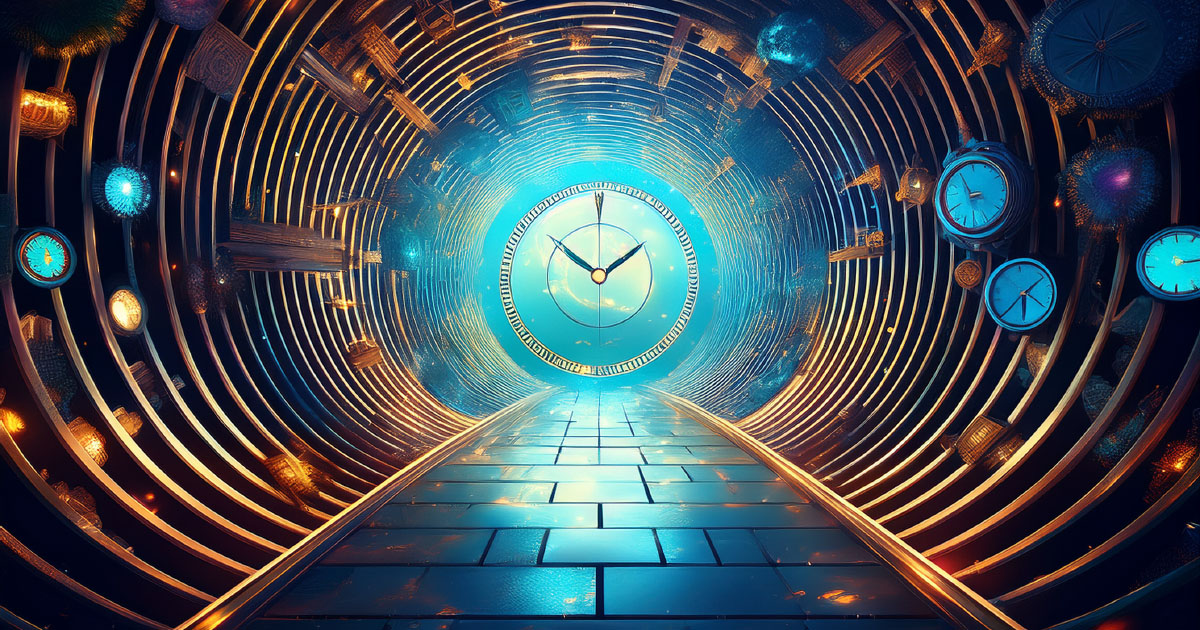――「募集わずか20人に、応募1142人」。
東京都が実施する「就職氷河期世代」対象の都職員採用試験で、倍率は57.1倍に達しました。数字だけでは語り尽くせない、この世代固有の挽回の難しさと再挑戦の意思が交錯しています。
思い出してください。新卒一括採用の門が最も狭かった時代、内定が得られず非正規や短期職を渡り歩いた履歴。家庭や介護、雇用調整に翻弄され、「次の一歩」を踏み出す機会を逃してきた人は少なくありません。だからこそ、公的領域での再スタートは、人生のやり直しだけでなく、社会の公正を問い直す試金石でもあります。
本稿では、今回の試験の数値やスケジュールを整理しつつ、歴史的背景と現在の労働市場がどう接続しているのかを物語とデータで解説。読了後には「何が課題で、どう備えるべきか」が明確になるはずです。
- 応募1142人/募集20人で倍率57.1倍:I類Bは64.1倍、III類は50.1倍
- 対象は1970/4/2〜1986/4/1生まれ。2020年度から毎年実施
- 選考は適性検査→面接。12月11日に最終合格発表
- 人手不足時代でも、高倍率になる理由は「職務適性」と「公的責務」
- 準備は職務理解・経験棚卸し・業務課題の言語化が鍵
9月3日に何が公表されたのか?
東京都人事委員会は2025年9月3日、今年度の「就職氷河期世代」対象・都職員採用試験(I類B=大卒程度、III類=高卒程度)の申込状況を公表しました。
募集は計20人、申込者は1142人(内訳:I類B 641人/III類 501人)。倍率はI類B 64.1倍/III類 50.1倍、総合で57.1倍です。
| 工程 | 日程 | 曜日 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 2025年10月5日 | 日 |
| 第1次合格発表 | 2025年11月7日 | 金 |
| 第2次試験 | 2025年11月29日 | 土 |
| 最終合格発表 | 2025年12月11日 | 木 |
受験票を前に震える手で戦略を見直す人もいれば、長年の業務経験をどう「都の仕事」に翻訳するかで悩む人もいます。
物語は個人の再挑戦であると同時に、自治体の人材確保という現場の課題とも深く結びついています。
すべては「就職氷河期」から始まった
対象は1970/4/2〜1986/4/1生まれ。新卒一括採用が厳格で、既卒・非正規への視線が冷たかった時代、最初の選択が一生を左右しがちでした。
東京都は2020年度から毎年、同世代向け採用を継続。民間で培った力を公共で活かせる再挑戦の回路を整えています。
数字が示す「門の狭さ」と昨年度比
| 試験区分 | 採用予定 | 申込者 | 倍率 | 昨年度倍率 |
|---|---|---|---|---|
| I類B(大卒程度) | 10人 | 641人 | 64.1倍 | 67.4倍 |
| III類(高卒程度) | 10人 | 501人 | 50.1倍 | 46.1倍 |
| 合計 | 20人 | 1142人 | 57.1倍 | 56.8倍 |
人手不足の時代でも、公務は職務適性や公的責務への意識が強く問われます。倍率が高止まりするのは、配属即戦力や行政手続の正確性を要求する職務特性が背景にあるからです。
なぜ「氷河期向け」だけが突出して厳しく見えるのか?
支援の公平性(年齢・世代を限定)と機会の是正(歴史的ハンディの補正)の間には緊張関係があります。
一方で「実務経験豊富で即貢献できる」期待も大きい。公務の安定性へのニーズと、公共価値の創出を求める都の要請が交差し、結果として高倍率になりやすい構造です。
「倍率の高さは需要の集中だけでなく、職務要件の明確さを反映します。
合否を分けるのは、①配属想定の業務理解、②自己の経験棚卸しと成果の定量化、③入庁後最初の90日で出す具体的アウトプット計画――この三点の一貫性です。」
SNS拡散が生んだ「情報過多」と学習の非効率
受験ノウハウが溢れる一方で、配属実務の解像度が低い情報も多く、学習が試験対策に偏重しがちです。
最新の要綱と公式資料を一次情報として起点にし、ポストに紐づく課題へ学習を寄せるのが最短距離です。
組織はどう動いたのか――制度の設計思想
東京都はI類B・III類それぞれで10人程度の採用枠を設け、適性検査→面接で多面的に評価。
年1回の継続実施で挑戦機会を恒常化させ、民間経験の活用による行政サービスの改善を狙います。
1) 職務理解:希望部局の中期計画・施策KPIを読み、自分の成果指標に翻訳。
2) 経験棚卸し:実績を数値・期間・関与度で記述(例:受付DXで待ち時間30%短縮等)。
3) 90日計画:着任〜3か月で可能な小さな勝ち(業務標準化・見える化・改善)をA4一枚に。
よくある質問(FAQ)
ポイント:年齢要件は毎年の要綱で再確認を。
昨年度比:I類Bは微減、III類は増。
準備:職務理解と「90日計画」を面接で語れるように。
Tip:部局のKPIと自分の過去成果を線で結ぶ。
やること3つ:①公式資料の精読 ②経験の定量化 ③着任90日計画の作成。
まとめ――狭き門でも、準備は戦略で広がる
倍率57.1倍という現実は重い。でも、職務理解×経験の翻訳×90日計画という三点セットは、門を押し広げる最短ルートです。
採用は入庁後の貢献の約束。あなたの物語が次に進むために、今日から一次情報を起点に準備を始めましょう。