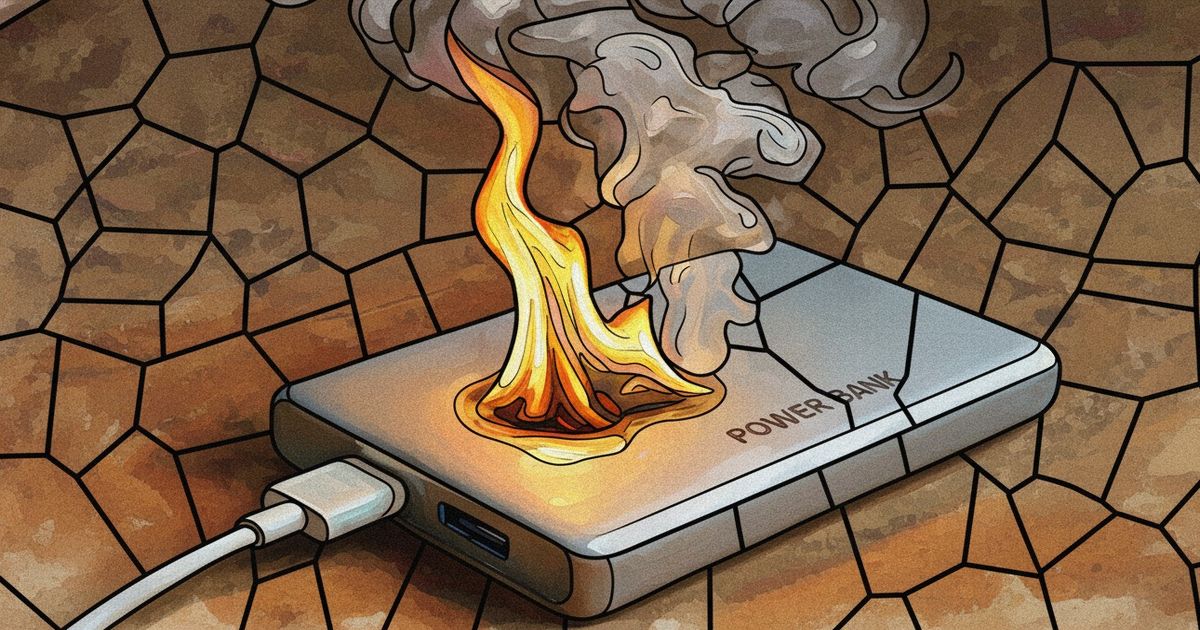※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。
あなたは、東京でクマが出たというニュースを聞いたことがありますか?
今、都内西部の日の出町などでツキノワグマの出没が相次いでいます。木に登り、柿を食べる姿がカメラに捉えられるなど、かつてない事態が続いています。
本来なら冬眠に入るはずのこの時期。なぜクマは冬を眠らずに過ごそうとしているのでしょうか? その背景には、気候変動と人間社会の影響が複雑に絡んでいるのです。
都内でクマが連夜出没 住民に不安広がる
東京・日の出町の住宅裏に設置された番組カメラが、2夜連続でツキノワグマを激撮しました。
体長1.5メートルほどの成獣が柿の木をスルスルと登り、実を食べる様子。翌日には100メートル離れた別の住宅でも目撃され、地域には「裏の窓を開けるのも怖い」といった声が広がっています。
これまで“山奥の生き物”とされていたクマが、ついに都市近郊で姿を見せ始めたのです。
背景にある「温暖化」と「食糧不足」
専門家によれば、今年の猛暑と暖冬傾向により、山のドングリやブナの実などクマの主食が極端に不作だったといいます。
「十分な脂肪を蓄えられないため、冬眠のスイッチが入らず、餌を探して動き続ける個体が増えている」と専門家は説明します。
さらに、放置された柿の木やゴミ、生ごみなど“人間が残した食べ物”が、クマを里へ誘っていると指摘。人の生活圏そのものが、クマにとっての“冬の食料庫”になっているのです。
「75年生きて初めて」住民が語る異変
日の出町のある住民は、「生まれてから75年、一度も見たことがなかった」と驚きを隠しません。
防犯カメラには深夜にクマが住宅街を歩く姿も映り、「まさか東京で」と多くの人が恐怖を感じています。犬が吠えても逃げず、ライトを照らしても動じない——人慣れしたクマが増えていることも懸念材料です。
行政と専門家が示す「共存型の対策」
秋田県では自衛隊派遣の検討にまで発展し、東京都も対策を強化しています。
山内准教授は「放置された柿の木は、実を早めに取るか伐採するのが望ましい」と助言。クマを誘引する要因を取り除くことが第一歩だといいます。
また、出没情報を共有する防災アプリやLINE連携など、地域住民同士での連携も広がっています。
・東京西部でクマの出没が急増
・暖冬と食糧不足で冬眠できない個体が出現
・人間の残す「食べ物」が誘因に
・柿の木やゴミの管理が最重要
・地域アプリでの出没情報共有が有効
SNSでは「信じられない」「怖すぎる」と話題
X(旧Twitter)では「東京にクマが出る時代か…」「人間が山を壊した結果だ」といったコメントが殺到。
一方で「共存のルールを学ぶ時」「柿の木を放置しないようにしよう」といった建設的な声も増え、SNSが防災意識を広げる役割を果たしています。
冬眠しないクマ 年越し活動の可能性も
本来11月から冬眠に入るツキノワグマですが、近年は冬でも活動を続ける個体が増加。
雪の中で柿を掘り出して食べたり、家畜用の餌をあさる様子も確認されています。
専門家は「今後、年を越して活動するクマが増える」と警鐘を鳴らしており、私たちも“冬でも油断しない”意識が必要です。
Q1. クマが冬眠しないのは異常現象ですか?
A1. はい。温暖化とエサ不足が重なり、冬でも活動を続ける個体が増えています。
Q2. もし都内でクマを見かけたら?
A2. 近づかずに静かに離れ、110番通報を。写真撮影は危険です。
Q3. 柿の木や果樹をどうすれば安全?
A3. 実を早めに収穫し、放置しないことが最善です。不要なら伐採も検討を。
Q4. 家の周りでできる防衛策は?
A4. 生ごみや餌の放置を避け、夜は屋外照明を点けておくことが有効です。
東京でもクマが冬眠せず活動する——それは自然と人の距離が近づきすぎたサインです。
「危ないから排除」ではなく、「どう距離を保つか」を考えることが、これからの都市防災の新しい形。
柿の木やゴミの管理を通して、人と野生の“静かな共存”を実現することが、今求められています。