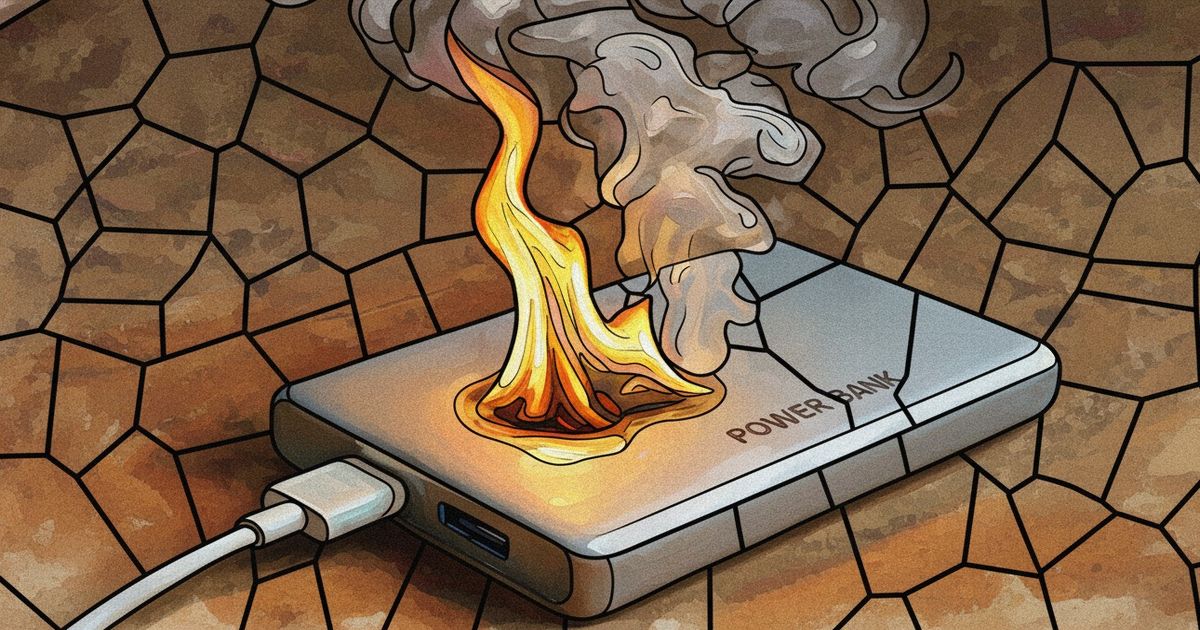※本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。
東京都青梅市の小学校で、1年生の児童ら22人がクロスズメバチに刺され病院に搬送されるというショッキングな出来事がありました。
全員が意識はあるものの、「なぜ学校で?」という疑問の声が相次いでいます。
本記事では、事件の背景とハチの生態、そして2025年以降に求められる学校安全対策を社会的視点で掘り下げます。
青梅市の小学校で児童ら22人が刺され搬送
10月23日午前9時半ごろ、青梅市今井小学校で「児童がハチに刺された」との119番通報が入りました。
屋外で「生活科」の授業をしていた小学1年生19人と教師3人が刺され、計22人が病院に搬送。全員意識はあるということです。
もし自宅や職場の近くにハチの巣を見つけたら、すぐに専門業者へ相談を。
【害虫害獣駆除】業界最安値に挑戦中!作業実績20万件突破
![]()
地中の巣を刺激か クロスズメバチの特徴
教育委員会によると、刺したのは地中に巣を作る「クロスズメバチ」とみられています。
この種は巣を守るための防衛本能が強く、落ち葉を拾う動作で地面を刺激すると一斉に攻撃することがあります。
秋は巣の防御性が最も高まる季節で、被害が集中する傾向にあります。
学校側の迅速対応で大事に至らず
刺傷後、学校職員がただちに119番通報し、救急搬送が行われました。
保護者や地域では「自然体験授業のリスク管理を見直すべきだ」との声も上がっています。
自宅の庭や倉庫などに巣ができるケースも多いため、プロの駆除サービスを活用するのが安心です。
![]()
- 青梅市の今井小で児童ら22人がハチに刺され搬送
- 原因は地中に巣を作るクロスズメバチ
- 全員意識あり、授業中の落ち葉拾いで発生
- 学校安全対策の再点検が急務に
「刺されたら冷やす・動かない」が鉄則
昆虫学の専門家は「まず安全な場所に避難し、刺針をピンセットで抜いて流水で洗い、冷やすこと」と説明します。
また、アナフィラキシーショックの兆候(息苦しさ・めまい・蕁麻疹など)が出た場合は、すぐに救急要請が必要です。
「ハチは刺激を与えなければ襲ってこない」という誤解が被害を拡大させているとも指摘されています。
SNSでは「自然教育と安全管理の両立を」
X(旧Twitter)上では、「自然体験授業の意義は大切」「でも安全対策も同じくらい重要」との意見が多く見られました。
一方、「学校ごとに危険生物マップを作るべき」「教員研修でハチの知識を取り入れて」など建設的な提案も広がっています。
自宅・公共施設での巣発見時は、素人判断せず専門家に相談しましょう。
🔍【害虫害獣駆除】24時間対応・最短即日訪問はこちら
![]()
2025年に向けた学校安全対策の強化
東京都や教育委員会では、野外授業前の安全点検や職員研修の拡充を進めています。
また、危険生物の生息情報を地域と共有する「生態情報ネットワーク」の導入も検討されています。
専門家は「自然と向き合う教育を続けながら、現場の安全文化を根付かせることが大切」と訴えています。
FAQ:ハチ被害と学校安全に関する質問
A1:スズメバチの一種で、体長は1〜1.5cmほど。地中に巣を作り、刺激に敏感です。
A2:刺針を抜き、流水で洗い、冷やす。呼吸困難や全身症状がある場合もあるので、すぐ救急要請を。
A3:授業前に現場確認を行い、巣を見つけたら専門業者に依頼。生徒にも「巣に近づかない教育」を。
青梅市でのハチ被害は、誰にでも起こり得る“身近な自然トラブル”でした。
2025年以降、教育現場には「自然に触れる学び」と「安全を守る教育」の両立が求められています。
自然と人間の共存を考える第一歩として、学校安全対策の再構築が急がれます。