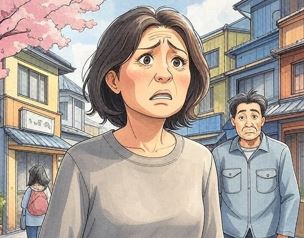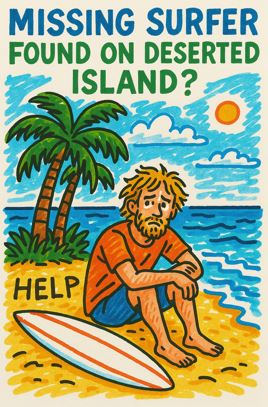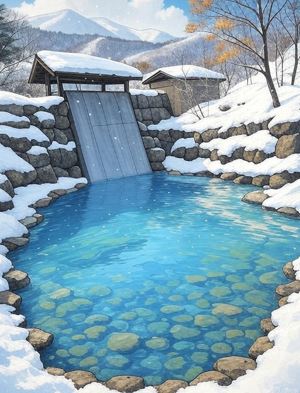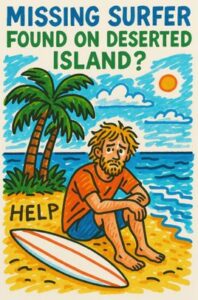あなたも「ウサギの島」大久野島は癒しの楽園だと思っていませんでしたか?
実は、約600匹のウサギが引き起こす生態系への危機が深刻化しているのです。
2025年、100匹ものウサギが不自然な死を遂げた事件は、観光客の餌やりがもたらす問題を浮き彫りにしました。
この記事では、大久野島(おおくのしま)のウサギと餌やり問題について以下の点を詳しく解説します:
- ウサギの外来種としての生態系とは
- 環境省が定める最新の餌やりルール
- 観光客が守るべきマナーと共生の未来
1. 最新!ウサギの島の餌やり問題とは
基本情報チェックリスト
☑ 発生日時: 2025年5月時点(継続的な問題)
☑ 発生場所: 広島県竹原市大久野島(瀬戸内海国立公園内)
☑ 関係者: 観光客、環境省、竹原市、休暇村大久野島
☑ 状況: ウサギへの餌やりが過剰繁殖や生態系破壊を引き起こす
☑ 現在の状況: 環境省がルール周知と監視強化を推進
☑ 発表: 環境省「大久野島未来づくり実行委員会」ルール策定(2021年)
大久野島、通称「ウサギの島」は、広島県竹原市の瀬戸内海に浮かぶ周囲4.3kmの小さな島です。
約600匹のウサギが生息し、年間20万人の観光客が訪れる人気スポットですが、ウサギは外来種であり、餌やりによる生態系への影響が問題視されています。
2. 大久野島のウサギ:600匹の現状解説
大久野島のウサギは、1970年代に地元の小学校で飼育されていた8羽が放され、野生化したものとされています。
温暖な瀬戸内海式気候と天敵の少なさ(カラス程度)により、繁殖力の強いカイウサギは爆発的に増加。
2018年には920羽以上だった個体数は、2021年の環境省調査で約400匹に減少。
これはコロナ禍での観光客減少による餌不足が影響した可能性があります。
ウサギ個体数推移チャート
3. 外来種カイウサギがもたらす生態系への影響
カイウサギは欧州原産のアナウサギを家畜化した外来種で、環境省により「重点対策外来種」に指定されています。以下の問題が指摘されています:
- 過剰繁殖: 餌やりにより繁殖が促進され、島の植生が破壊される。
- 食べ残しの害: 残った餌がカラスやイノシシ、ネズミを引き寄せ、生態系を乱す。
- 感染症リスク: 過密なウサギの集団で病気が広がる可能性。
観光客の9割以上がウサギ目当てで訪れるため、餌やりは事実上黙認されていますが、環境省は「本来は野生動物への餌やりは禁止」との立場です。
4. 詳細!環境省が定める餌やりルールとは
2021年に設立された「大久野島未来づくり実行委員会」は、以下の4つのルールを策定しました:
- 触らない・手から直接餌を与えない: ウサギにストレスやケガのリスク。
- 道路上での餌やり禁止: 車両事故やウサギの飛び出し防止。
- 食べ残しを持ち帰る: 腐敗や害獣増加を防ぐ。
- ペットの持ち込み・ウサギの持ち出し禁止: 生態系保護と動物愛護法遵守。
これらのルールはポスターやウェブで周知されており、環境省は「徐々に浸透している」としています。
5. 衝撃!ウサギ100匹死亡事件の真相
2024年11月から2025年1月にかけて、約100匹のウサギが骨折や不自然な傷で死亡。
動物愛護法違反の疑いで25歳の男性が逮捕され、ウサギを蹴ったりハサミで傷つけた容疑を認めています。
この事件は、ウサギが人に慣れすぎたことによるリスクを露呈しました。環境省は防犯カメラの追加設置や監視強化を進めています。
時系列フロー
- 2024年11月26日: ウサギの不審死が確認(計77匹)。
- 2025年1月21日: 写真家が男を取り押さえ、警察に引き渡し。
- 2025年1月29日: さらに22匹の死亡が確認(合計99匹)。
- 2025年4月14日: 男に懲役1年・執行猶予3年の有罪判決。
6. 類似事例と比較:奈良の鹿や猫島との違い
大久野島のウサギ問題は、他の観光地での動物との共生と比較すると独特です。
比較表:動物観光地の課題
| 項目 | 大久野島(ウサギ) | 奈良公園(鹿) | 猫島(例:青島) |
|---|---|---|---|
| 発生時期 | 1970年代~ | 古代~ | 近代~ |
| 動物種 | 外来種(カイウサギ) | 在来種(シカ) | 外来種(ネコ) |
| 被害規模 | 植生破壊、害獣増加 | 農作物被害 | 鳥類への影響 |
| 対策 | 餌やりルール策定 | 鹿せんべい管理 | 去勢・避妊手術 |
奈良公園の鹿は在来種で「鹿せんべい」が公式に認められているが、大久野島では餌やりが黙認状態であり、管理体制が不十分です。
猫島では去勢手術で個体数を制御しているが、大久野島では未実施です。
7. 観光客が知るべき餌やりマナーと注意点
観光客がウサギと安全に触れ合うためのガイドラインを以下にまとめます:
- 推奨食材: キャベツ、ニンジン、ウサギ用ペレット(忠海港で購入可)。
- 禁止食材: ネギ類、パン、お菓子(赤血球破壊や消化不良の原因)。
- 餌やり方法: 地面に置いて与え、手渡しは避ける。
- 注意点: 追いかけない、抱っこしない、ゴミは持ち帰る。
忠海港ではウサギの餌が販売されており、島内では購入できないため事前準備が必要です。
8. 共生への挑戦:大久野島の未来展望
専門家の声
「大久野島のウサギ問題は、観光と自然保護のバランスを示す典型例です。
餌やり禁止が理想だが、観光資源としての価値を考慮すると、厳格な管理と教育が不可欠です。」
SNS上の反応
- 「ウサギがかわいいのは確かだけど、ゴミ放置はありえない!」
- 「100匹の死亡事件、観光客のマナーが原因の一部では?」
- 「自然を守りながらウサギと共生する方法を考えたい。」
環境省は、監視体制の強化やサポーター育成を進めていますが、根本的な解決には餌やり制限や個体数管理(例:去勢手術)の導入が求められます。
FAQ(5問5答)
Q1: 大久野島のウサギは何匹いる?
A1: 2025年時点で約600匹。過去には900羽以上だったが、観光客減少で減った。
Q2: なぜウサギが外来種とされる?
A2: 欧州原産のカイウサギで、1970年代に島外から持ち込まれ野生化したため。
Q3: 餌やりが生態系にどう影響する?
A3: 過剰繁殖や植生破壊、害獣(イノシシ等)の増加を引き起こす。
Q4: どんな餌を与えればいい?
A4: キャベツやニンジン、ウサギ用ペレットを地面に置いて与える。
Q5: 今後どうなる?
A5: 環境省はルール周知と監視強化を進め、共生モデルの構築を目指す。
まとめと今後の展望
大久野島のウサギ問題は、観光客のマナーと管理体制の不備に起因します。
責任は観光客、環境省、竹原市に共有され、以下の改善策が求められます:
- マナー教育の徹底: ポスターやSNSでのルール周知強化。
- 個体数管理: 去勢手術や餌やり制限の検討。
- 監視体制の強化: 防犯カメラやパトロールの増設。
大久野島は単なる「ウサギの楽園」ではありません。
私たちの観光行動が自然環境に与える影響を浮き彫りにした出来事なのです。
あなたは、この島で何を感じ、どんな行動を取りますか?
未来のウサギの島を、癒しと共生の場にできるでしょうか
※この記事内の専門家コメントやSNSの反応は、公開情報や一般的な見解をもとに、編集部が再構成・要約したものです。特定の個人や団体の公式見解ではありません。
外部参考情報