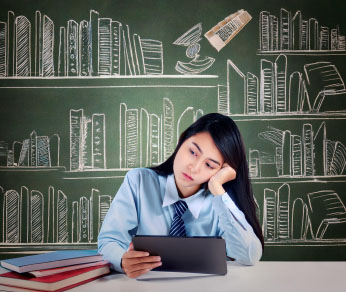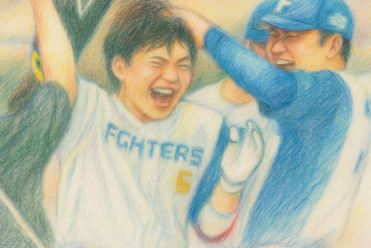医療や介護の現場で働く人々が今、深刻な「ペイシェントハラスメント(ペイハラ)」の被害に悩まされています。
患者や家族による暴言や不当な要求、誹謗中傷などが日常化し、働く人たちの心身をむしばむ実態が社会問題となりつつあります。
この記事では、近年特に注目されているペイハラの実態と、それに対する法的整備や自治体、病院、政府の取り組み、そして企業や報道の影響などを多角的に解説します。
対応策を考える上での課題と展望を整理し、医療従事者の尊厳を守るために私たちにできることを考える一助としてください。

ペイハラの定義と実態
ペイシェントハラスメント、通称ペイハラとは、患者やその家族が医療従事者や介護スタッフに対して暴言や暴力、不当な要求、あるいは誹謗中傷などを行う行為を指します。
特に近年では、SNSや口コミサイトなどのネット空間での誹謗中傷が拡大しており、現場のストレスや離職リスクが急激に増しています。
例えば、外来での長時間待ちに対して怒鳴る、医療ミスと関係のないことで病院の評判を落とすような書き込みをする、対応が気に入らないという理由で暴言を吐くといった事例が報告されています。
これは単なるクレームではなく、明確なハラスメント行為として法的にも対応が必要とされています。
背景にある労働環境の問題
このようなハラスメント行為が深刻化する背景には、医療や介護現場の慢性的な人手不足、長時間労働、精神的な負担の蓄積などがあります。
厚生労働省や各自治体が提示するガイドラインだけでは現場の改善に結びついていないという指摘も少なくありません。
これらの問題が相まって、ペイハラにさらされた職員が孤立しやすくなり、離職へとつながってしまう悪循環が続いています。
日本医師会の相談窓口設置と法的支援体制の強化

ネット上の誹謗中傷に対応する新制度
日本医師会は、医療機関や従事者がネット上の誹謗中傷や不当要求に悩まされている現状に対応し、2025年に「ペイシェントハラスメント・ネット相談窓口」を開設しました。
この相談窓口では、匿名での相談が可能であり、必要に応じて弁護士や労働基準監督署と連携する仕組みが構築されています。
Googleマップの口コミ機能やSNSでの悪質な書き込みによって、医療機関のイメージダウンや人材確保の困難さが浮き彫りになったことがこの対応のきっかけです。
相談窓口の設置は、従来見過ごされがちだったネット上のハラスメントに対する実質的な対抗手段として注目されています。
法的整備と対応指針の見直し
これと並行して、厚生労働省もペイハラを明確に定義し、対応のマニュアル作成や教育機関での研修導入を進めています。
今後は、加害者に対する法的措置や損害賠償請求が実効性を持つよう、具体的な判例や運用事例が整えられることが求められます。
自治体と病院による独自の対策の推進

富山市の条例制定と基本方針策定
ペイハラ対策では、富山市の野村病院の取り組みが全国的に注目を集めています。
野村病院では、「ハラスメント防止条例」と「基本方針」を導入し、地域と連携した実効的な対策を構築しています。
このような条例は全国でも初の取り組みであり、今後のモデルケースとして期待されています。
同病院では「早期対応」「記録保存」「チーム連携」「外部機関との連携」という4原則に基づいてハラスメントへの対応を実施。
問題が発生した際にはすぐに記録を取り、職員間で共有し、専門家との連携を取ることで職場の安全を確保しています。
他自治体での取り組みの広がり
その他の自治体でも、ハラスメント防止マニュアルの作成や、職場環境の実態調査などが進められています。
例えば大阪府や東京都内の一部医療機関では、医療従事者を対象に定期的なアンケート調査を行い、問題の早期発見と共有を目指すなど、独自の対策が進められています。
ペイハラ未対策職場の課題と従業員の声

対策がない職場の多さとその背景
パーソル総合研究所が行った調査によると、ペイハラを受けたと答えた従業員のうち約40パーセントが「職場に対策がない」と回答しました。
さらに、約60パーセントの職場では、対策の有無すら従業員に周知されていないことが判明しています。
この背景には、管理職の理解不足や、問題を表に出すことへのためらいなどがあります。
特に小規模な医療機関や介護施設では、組織としての対応力に限界がある場合も多く、従業員が個別に問題に対処せざるを得ない現実が浮かび上がっています。
対策導入が進まない要因
対策が遅れる要因として、リソースの不足や法的知識の不足が挙げられます。
また、ハラスメントが感情や文化的背景に根差す場合もあり、単純なマニュアル化では対応しきれないケースもあります。
従って、対策には現場ごとの柔軟な対応と、制度的な支援の双方が求められます。
メディア報道が生む社会的関心と行動変化

広末さん逮捕報道とペイハラ問題の注目
2025年4月に報道された広末さんの逮捕報道が、社会の注目を再びペイハラ問題へと向けさせました。
報道内容そのものは医療ハラスメントとは直接関係ないものの、SNS上では「医療関係者への過度な要求も同様に問題だ」といった意見が広まり、改めて対策の必要性が議論されました。
報道の影響によって、一般の人々の認知度が一段と高まり、医療従事者を取り巻く労働環境への理解と支援の動きが加速しています。
報道の力を生かした啓発活動の必要性
こうした報道を一過性の話題で終わらせるのではなく、継続的な啓発活動や教育に活かすことが重要です。
報道機関は単にニュースを伝えるだけでなく、背景にある構造的な問題や解決策を伝える役割を果たすことが求められています。
今後の課題と社会全体で取り組むべき方向性

ペイハラは一部の悪質な行為にとどまらず、医療や介護という社会の基盤を揺るがす問題です。
今後は、法整備のさらなる充実とともに、患者や家族、そして社会全体が医療従事者への理解と敬意を持つことが不可欠です。
行政は指針にとどまらず、実際に使える仕組みとしての整備を行う必要があります。
また、医療機関内部でも相談体制の強化、職員のメンタルケア、教育機会の確保などが求められます。
働く人が安心して患者と向き合える環境づくりが、結果的に医療サービスの質を高め、社会全体の安心につながるのです。
まとめ
- ペイハラは、医療介護従事者の離職や疲弊を招いています。
- 日本医師会は、ネット相談窓口を開設して支援を強化しています。
- 富山市をはじめとした自治体が、先進的な条例を導入しています。
- 約40パーセントの職場では、対策が未整備であることが課題です。
- メディア報道を契機に、社会的な関心が高まっています。
- 法整備と現場の柔軟な対応の両輪が、今後のカギとなります。