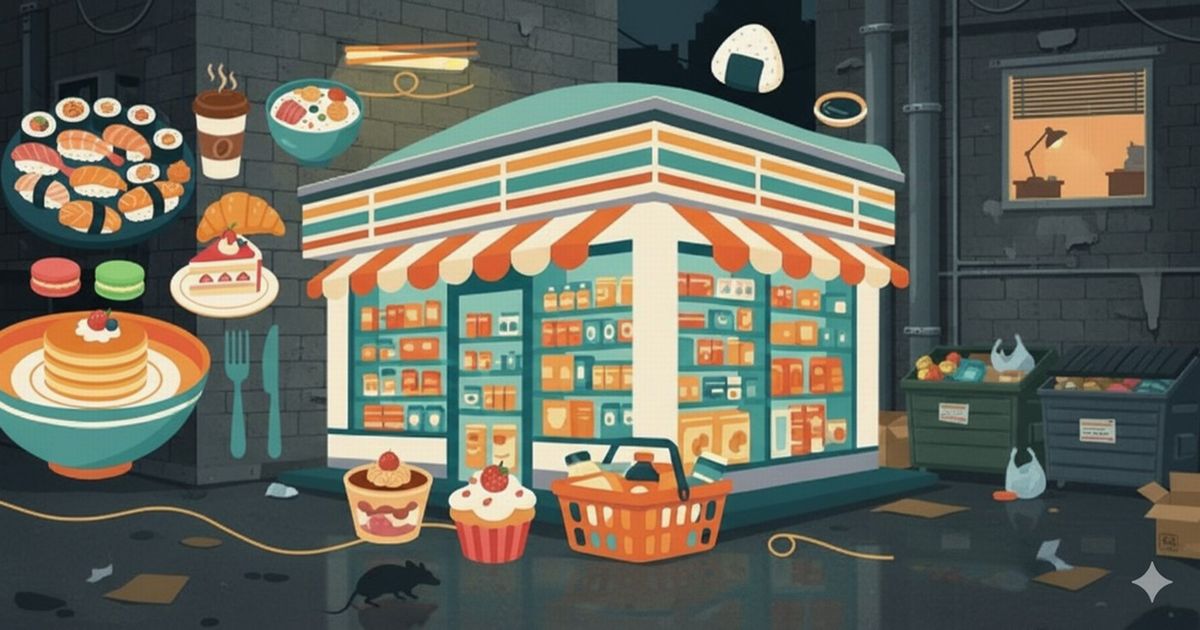北海道の名産エゾバフンウニが記録的な不漁に直面し、価格が急騰しています。
あなたはウニ丼が2万円を超える事態を想像していましたか?
実は、2025年の競りでは100gで2万9,000円という驚愕の価格が記録され、5年前の約4倍に跳ね上がりました。
この記事では、エゾバフンウニの不漁問題とその背景にある海水温上昇や磯焼けについて、以下の点を詳しく解説します:
- 不漁の現状と価格高騰の詳細
- 海水温上昇と磯焼けの影響
- 漁業者の取り組みと今後の展望
エゾバフンウニ不漁の衝撃的現状
北海道のウニ漁は深刻な危機に瀕しています。特にエゾバフンウニの漁獲量が激減し、飲食店や消費者にも大きな影響を与えています。
基本情報チェックリスト
- 発生日時: 2025年6月~8月(ウニ漁解禁期間)
- 発生場所: 北海道後志地方(余市町、積丹町、礼文島など)
- 関係者: 漁業者、飲食店(例:うに丼専科うにどころ新岡商店)、消費者
- 状況: エゾバフンウニの漁獲量が過去5年で約7トン減少し、2024年には9割がキタムラサキウニ
- 現在の状況: 価格は100gで最高2万9,000円、ウニ丼は2万2,000円超
- 発表: 北海道大学大学院水産科学研究院による磯焼けと海水温上昇の影響報告
不漁と価格高騰の詳細な時系列
エゾバフンウニの不漁は数年前から顕著になり、2025年は特に深刻な状況です。以下は時系列での状況です。
- 2021年秋: 北海道太平洋沿岸で史上最悪の赤潮が発生。ウニ被害額は約74億円に達した。
- 2023年: エゾバフンウニの価格が急上昇。2~3年前から異変が顕著に。
- 2024年6月: 後志地方でウニ漁の9割がキタムラサキウニ、エゾバフンウニの漁獲量が前年比約10分の1に減少。
- 2025年6月~7月: 礼文島でエゾバフンウニの漁獲量が前年同期の半分、浜値が2倍に高騰。
- 2025年7月: 競りで100gあたり2万9,000円を記録。ウニ丼の価格が2万2,000円超に。
漁師の成田博氏は「60年、70年やっている人たちもこんな年はない」と異常性を強調。飲食店では競り負けが頻発し、仕入れが困難な状況が続いています。
海水温上昇と磯焼けの深刻な影響
海水温の上昇と磯焼けが、エゾバフンウニの不漁の主因と考えられています。この現象は海の生態系に大きな変化をもたらしています。
比較表:エゾバフンウニとキタムラサキウニの違い
| 比較項目 | エゾバフンウニ | キタムラサキウニ |
|---|---|---|
| 生息環境 | 冷水性を好む | 温暖な海水でも生存可能 |
| 漁獲量 | 2024年で前年比約10分の1 | 2024年で全体の9割を占める |
| 価格 | 100gで2万9,000円(2025年最高値) | 100gで3,000~5,000円 |
| 味の特徴 | 濃厚な甘み、磯の香り | あっさりした上品な味わい |
エゾバフンウニは冷水性のため、海水温が平年より3~4℃高い環境では生存が困難。キタムラサキウニは適応力が高く、漁獲量が安定している。
磯焼けの原因と影響
北海道大学大学院水産科学研究院の浦和寛准教授によると、海底の海藻がほぼ見えない「磯焼け」状態が深刻化しています。
ウニのエサとなるコンブが減少し、エゾバフンウニの身入りが悪化。海水温は過去3年間、6~8月に平年を3~4℃上回り、記録的な暑さが続いています。
漁業者の対応と社会的反響
漁業者や研究機関は、不漁への対策を模索しています。社会的にも注目を集めるこの問題について、専門家や消費者の声を見てみましょう。
専門家の声
「エゾバフンウニは冷水性のウニで、海水温の上昇は生存に深刻な影響を与えます。磯焼けの進行は海藻の減少を加速させ、ウニのエサ不足を引き起こしています。
SNS上の反応
- 「ウニ丼2万円超とは衝撃!高級食材すぎて手が出せない…」
- 「海水温上昇でこんな影響が出るとは。環境問題が身近に感じる」
- 「このままじゃエゾバフンウニが幻の食材になってしまうのが心配」
SNSでは価格高騰への驚きと、環境問題への懸念が広がっています。消費者の間でも、エゾバフンウニの希少性が話題に。
FAQ:エゾバフンウニ不漁の疑問を解消
Q1: エゾバフンウニの不漁はいつから始まった?
A1: 2021年の赤潮被害をきっかけに顕著になり、2023年以降さらに悪化。2024年は前年比約10分の1に。
Q2: なぜエゾバフンウニだけが不漁なの?
A2: 冷水性を好むエゾバフンウニは、海水温上昇に弱く、磯焼けによるエサ不足も影響。
Q3: 価格高騰は消費者にも影響する?
A3: ウニ丼が2万2,000円超となり、高級飲食店でも提供が困難に。一般消費者には手が届きにくい。
Q4: 不漁への対策は進んでいる?
A4: 泊村栽培漁業センターで稚ウニ約200万個を放流。3年で水揚げ可能な大きさに育つ。
Q5: 今後エゾバフンウニは復活する?
A5: 栽培漁業や藻場再生が鍵だが、海水温上昇の抑制が不可欠。長期的な改善が必要。
栽培漁業と藻場再生の取り組み
泊村栽培漁業センターでは、人工授精で育てた約200万個の稚ウニを放流し、3年後の水揚げを目指しています。
しかし、ヒトデやカニなどの外敵や高水温の影響で、生存率は課題です。
また、北海道登別市では藻場再生プロジェクトが進行中。ウニ保護のためのクレジット導入も検討されています。
比較表:過去の不漁対策と現状
| 比較項目 | 2021年赤潮対策 | 2025年不漁対策 |
|---|---|---|
| 発生時期 | 2021年秋 | 2024~2025年 |
| 被害規模 | ウニ被害額74億円 | 漁獲量前年比10分の1 |
| 原因 | 赤潮(カレニア・セリフォルミス) | 海水温上昇、磯焼け |
| 対応状況 | 漁業補償、調査強化 | 稚ウニ放流、藻場再生 |
赤潮は一過性の被害だったが、現在の不漁は慢性的な環境変化による。対策の長期化が求められる。
まとめと今後の展望
エゾバフンウニの不漁は、漁業者、飲食店、消費者に深刻な影響を与えています。
責任は気候変動による海水温上昇と、それに伴う磯焼けにあります。以下の改善策が急務です:
- 海水温抑制: 温室効果ガス削減による海洋環境の保護
- 藻場再生: コンブなどの海藻を増やす取り組みの拡大
- 栽培漁業の強化: 稚ウニの生存率向上と放流規模の拡大
情感的締めくくり
エゾバフンウニの不漁は、単なる価格高騰の問題ではありません。
私たちの食文化と海洋環境に潜む深刻な危機を浮き彫りにした出来事です。
このままでは、北海道の誇る名産が「幻の食材」となる日も遠くありません。
あなたは、この海の異変から何を学び、どのような未来を守りたいと思いますか?